No.114 こけら落とし公演 いよいよ大詰め!
一ヶ月間に渡り開催された、こまつ曳山交流館みよっさの、こけら落とし公演も、いよいよ大詰め。本日は三味線の発表会でした。「歌舞伎のまち・小松市」の通年発信に向け、これから真価が問われますね。


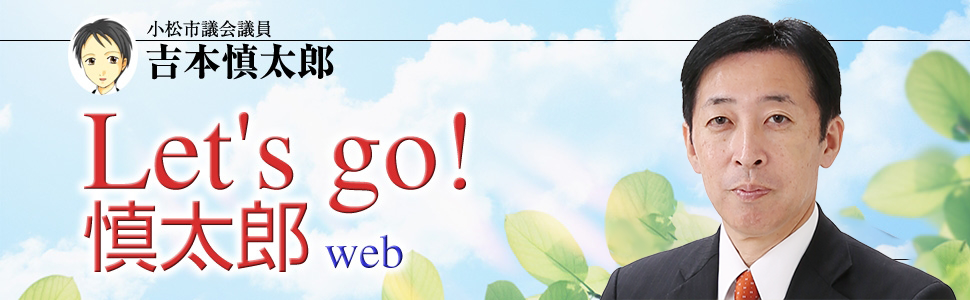
HOME ≫ ブログページ ≫
一ヶ月間に渡り開催された、こまつ曳山交流館みよっさの、こけら落とし公演も、いよいよ大詰め。本日は三味線の発表会でした。「歌舞伎のまち・小松市」の通年発信に向け、これから真価が問われますね。


小松市全市一斉美化の日に合わせ、白嶺町でも早朝より、泥あげとゴミ・空き缶拾いを実施しました。共に汗を流す事で、町民同士の連携・団結力が深まりますね。

小松市民ギャラリールフレにて。この書展も本年で20年を迎えるそうです。代表の蔵 桃苑 先生はじめ、会員の皆さんの楷書、行書、草書等の力作が展示されています。児童・生徒の作品も並び、小松市の文化の成熟度が良く分かります。

爽やかな青空の下、安宅小学校・御幸中学校の新校舎落成式が執り行われました。どちらの校舎も、約半世紀ぶりの新校舎。未来への半世紀に向けての、勉学・育成の場になってほしいですね。


ホテルサンルート小松にて。芦城東地区交通安全推進隊長として出席。平成25年度の小松市交通安全市民運動のスローガンは、交通マナーアップ「こまつ」。来賓挨拶の中で、和田市長が話していましたが、交通マナーは、中国語で「文明」と書くそうです。成程、小松市の文明度が問われますね。「気をつけて 母の一言 お守りだ」小松市交通安全標語最優秀作品の一つです。

小松商工会議所にて。大型店対策は連盟として避けられない課題です。しかし、本来の活動主体である、まちづくりと商業の活性化、商店街活性化事業の推進を、おざなりにしてはいけません。大和小松店跡地活用をはじめ「ピンチをチャンス」に変える方策を今こそ希求すべきです。

今週は、各種団体の総会に出席する事が多いです。小松能美保護区保護司会総会は、小松市第一地区コミュニティセンターにて開催。保護司としての処遇支援活動の推進と共に、グッドマナーキャンペーン、社会を明るくする運動等、犯罪予防活動の推進への取り組み等が報告されました。

串工業団地の分譲について、平成25年度「農地・立地防災月間」について、「空の駅こまつ」について、こまつ・アグリウェイプロジェトについて、お旅まつり曳山曳揃え事業について、小松市社会福祉事業団3施設の指定管理者変更について等、各部各課の報告を受けて、活発な質疑応答が交わされました。
毎年恒例の上本折町グラウンドゴルフ大会に特別参加。多太神社内に造られた、山あり、草むらあり、参道ありの超難コース(?)に四苦八苦。町内会の皆さんの歓声と笑顔が満ち溢れました。私のスコアは今年も…(T_T) でした。


本日5月18日付けの北國新聞朝刊、ワイド石川紙面に、「芭蕉の俳句で絵手紙を」記事が掲載されています。是非ともご一読ください。新聞、テレビ、インターネット等、現代社会の発信ツールは、より多様化し細分化しています。情報をいかに正確に、効果的に伝播出来るか、いかに使いこなせるかが、これからの時代、問われてきますね。

スマートフォンからのアクセスはこちら