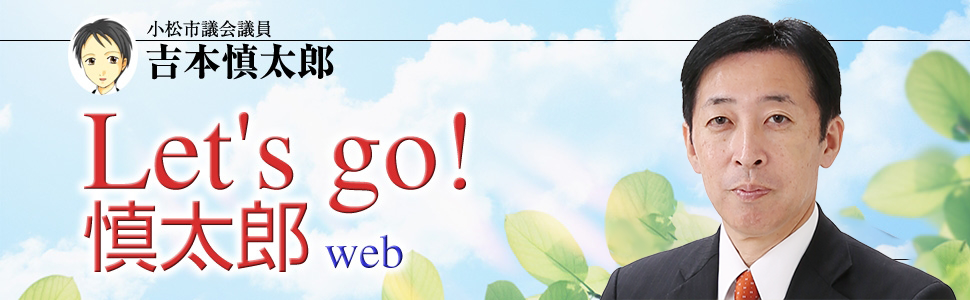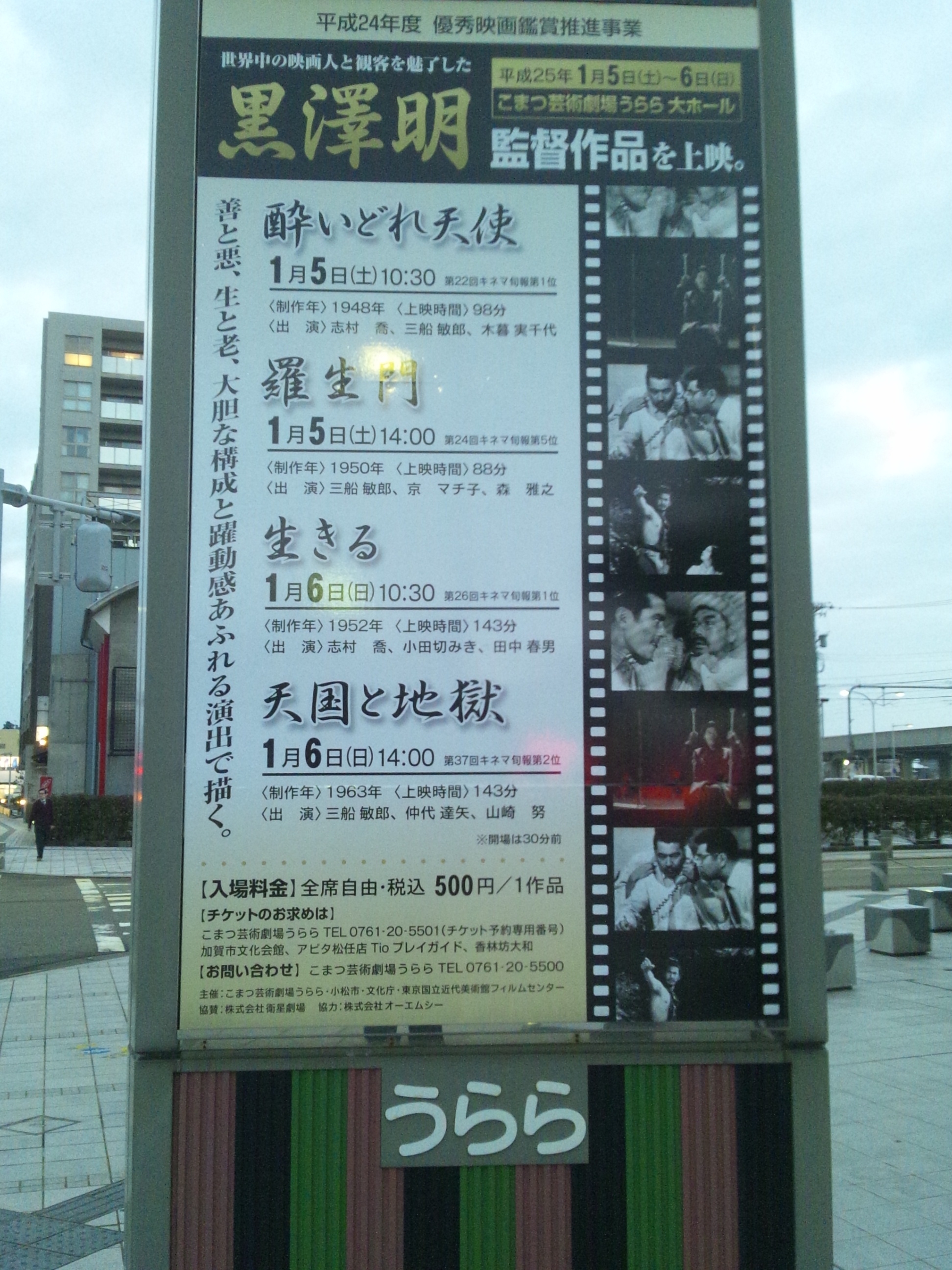No.014 1月 経済環境常任委員会
「空の駅こまつ」について、平成25年度産米の需要量確定について、小松市におけるごみ減量化の取組について、こまつ・のみ合同就職説明会の結果について、こまつ里山ワークショップの開催について、飯山市との観光交流都市協定について、こまつ学生ビレッジパスポートについて、小松空港国際線ターミナルの改修及び第2国際線駐車場の整備について、第15回 全国子供歌舞伎フェスティバルin 小松の開催内容について等、所管事項について、各部課の報告があり、それを受けて、活発な質疑・討論が行われました。